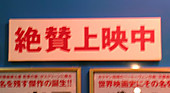ヨコハマ ストーリー 第18回 「国際劇場会館物語」
魅力あふれる街、ヨコハマ。
この街が、世界の表舞台に登場したのは、今からおよそ150年前。ペリー艦隊が来航したときから、その歩みは始まりました。そして今もヨコハマは、ユニークな街であり続けています。そんなヨコハマの由緒あるスポットを舞台に、物語と音楽で紡いでいく『ヨコハマ・ストーリー』。今日は「横浜国際劇場会館物語」
横浜、野毛。今は場外馬券場「wins」になっている場所にかつて横浜ショービジネスの中心として観客を魅了し、数々の伝説を生んだ横浜国際劇場会館があった。
昭和23年。横浜国際劇場会館一周年記念特別興行。小唄勝太郎の前座で登場したのはわずか十歳の少女だった。スポットライトをあびた彼女は、笠置シヅ子の「セコハン娘」などを歌った。およそ2千人の観客は驚き、そして割れんばかりの拍手を送った。美空ひばり、表舞台登場の瞬間であった。このステージをきっかけに、美空ひばりは、横浜国際劇場会館と約半年間の専属契約を結んだ。また映画『悲しき口笛』は、野毛周辺が舞台になり、それにちなみ劇場跡地の道路をはさんだ向かい側に、シルクハットをかぶった美空ひばりのブロンズ像が建っている。この劇場は、階段状の客席に絨毯が敷かれた立派なホールで、観客が戦後の暗い世相を瞬時忘れることができる空間であった。
「母が倒れた」という知らせを受けたのは、劇場での仕事が無事終った楽屋だった。マネージャーの北里さんが、落ち着いて話してくれた。私が司会をつとめるクラシックコンサートが始まる寸前に知らせが入ったのだが、北里さんは黙って舞台を見守り続けた。その判断に救われたかもしれない。
なぜなら、私は、モーツアルトの「レクイエム」の説明をしなくてはならなかったのだ。もし母のことを知ったら、不吉な想像をして、きっと声をつまらせてしまったことだろう。
急いでタクシーに乗り、流れていく風景を見ながら母をひたすら案じた。
母は、劇場に足を運ぶのが大好きだった。昭和31年、美空ひばりが8年ぶりに横浜国際劇場会館に出演した姿を観たことが何よりの自慢で、私が生まれてからも芝居、リサイタルと劇場通いはやめなかった。私が、劇場と縁がある仕事をしているのも、少なからず母の影響なのだ。私が司会をつとめる舞台には、必ず足をはこんでくれた。
病室の母は安定していた。パイプ椅子を広げて座ると母が目を覚ました。
「痛む?」と聞くと、「だいじょうぶ」と小さく言った。そして「コンサートは、うまくいった?」と聞かれ私は大きくうなずいた。母は、幸せそうに微笑んだ。
「初めて、お芝居に連れていったときのことを思い出すわ。騒ぐことも退屈がることもなく、黙って、じっとお芝居を観ていた。今でもその横顔を覚えている。客席から舞台に立つあなたを見ると、ほんとうに幸せな気持ちになるの。そしてね、あなたを自慢に思ってるのよ」と母が言ったとき、不覚にも涙がこぼれた。
今日の「横浜国際劇場会館物語」いかがでしたか。出演、小林 節子 脚本、北阪昌人でお送りいたしました。「ヨコハマ・ストーリー」また来週をお楽しみに・・・